
早川眞一郎
まずはじめに、次のような架空の事例を想像してみよう。
米国人女性・ミッシェルと日本人男性・カズオは、7年前に結婚して以来、米国ニューヨーク市で一緒に暮らしてきたが、1年前に離婚し、ニューヨーク市内でそれぞれ別の場所に住むことになった。2人の間には、ジョーという名の現在4歳の男の子が1人いる。2人の離婚に際して、ジョーは、母親ミッシェルと暮らすが、隔週の週末は父親カズオの家で過ごすこととなった。カズオは、仕事の関係で日本に帰国することになり、半年前のある週末に、自分の家に来ていたジョーを、ミシェルには相談せずに、日本に連れ帰った。その後、カズオは、日本にある実家(自分の父母の家)でジョーを育てている。母親ミッシェルは、どのようにしたらジョーを米国に取り戻すことができるだろうか。
この事例で生じたような事象は、通常「子の奪取」と呼ばれる。「子の奪取」とは、関係が破綻した男女の間に未成熟子(16歳程度までの子)がいるときに、一方の親やその親族などが、もう一方の親など監護権を有する者と暮らしている子を、実力で(つまり双方の合意や法的な手続によらずに)自分の手元に奪い去ることをいう。子の奪取は、たとえばともに日本に住む元夫婦間で子を奪い合うときのように、国内的な事件としても頻繁に生じるが、上記の事例のように国境を越える国際事件として発生することもある。そして、20世紀後半には、社会や家族の国際化とともに、このような国際事件としての子の奪取が、重要な社会問題として注目を集めるようになってきた。
そこで、このような国際的な子の奪取に対応するために、1980年にハーグ国際私法会議という国際機関において、ある条約が制定された。これが、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants; Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)」である。この条約は、1983年に発効し、その後も順調に締約国が増加して、2009年8月26日現在で81カ国が締約国となっている。米国についてこの条約が発効したのは1988年であるが、日本はまだ締約国になっていない。なお、締約国のリストは、ハーグ国際私法会議のウェブサイトに示されており、またこの条約に関する詳しい情報(条文、解説、文献等)も同ウェブサイトで見ることができる。
さて、この条約がどのようなものであるかを、上記の事例に即して概観してみよう。
まず、現在の状態、つまり米国が締約国であり、日本が締約国ではない状態ではどのようになるだろうか。現在、日本は締約国ではないので、日本と米国の間ではこの条約は適用されない。したがって、後述するような、条約を活用した解決を図ることはできない。そこで、母親ミッシェルの取りうる手段は、自ら父親カズオと話し合ってジョーを返還するよう求めるほかは、日本の裁判所において、日本の法制度に基づいて返還を求めることだけである。ところで、日本の裁判所にジョーの返還を求める申し立てをするには、日本の弁護士に依頼する必要がある。弁護士を使わずに申し立てることも制度上は可能であるが、日本語を解さず、日本の法制度を知らないミッシェルが、日本の弁護士を雇わずに裁判所を利用することは実際には不可能であろう。ミッシェルが日本で弁護士を探してこの事件を依頼するには、かなりの手間と費用を要することになる。さて、首尾よく日本の弁護士に依頼して、裁判所への申し立てをすることができたとしても、結果としてジョーの返還が認められるかどうかは、わからない。日本法上、両親間の子の奪取の事案において返還を認めるか否かを決する法制度は複雑なので、ここではその詳細の説明は省略するが、日本の裁判所は、この事案のあらゆる事情を考慮したうえで、「子の最善利益(best interest of child)」を図るには返還を命ずるべきか否かを判断することになる。そして、その「この事案のあらゆる事情」として判断の基礎になる事情のなかには、ジョーにとって、日本で父親カズオ(とカズオの父母)のもとで育てられるのと、米国で母親ミッシェルのもとで育てられるのと、いずれがより適切であるかについての判断も含まれる。したがって、裁判官が、いまジョーを米国のミッシェルのもとに返すよりも、このまま日本のカズオのもとで育てられるほうがよいと判断すれば、ミッシェルの申し立ては認められないことになる。
では、もし仮に日本も子奪取条約に加入しているとしたら、どうなるだろうか。その場合には、日米ともに締約国であるから、この事例にハーグ子奪取条約が適用されることになる。そうすると、この事例の処理は、上記のものとは大きく異なることになる。
条約が適用される場合の処理の流れは、おおむね次のようになる。ミッシェルは米国の「中央当局」(国務省の担当窓口)に相談して申し立てをする。すると、米国の中央当局から連絡を受けた日本の中央当局が、条約の仕組みに従ってジョーを米国に迅速に返還するために、強力な援助を提供してくれることになる。すなわち、日本の中央当局は、必要に応じてジョーとカズオを探し出して、カズオに任意の返還を促し、もしカズオがそれに応じない場合には、日本の裁判所に返還命令を求める裁判を自ら提起し、またはミッシェルがその裁判を提起するためのさまざまな援助を提供する。そして、その裁判において、日本の裁判官は、「ジョーにとって日本で父親カズオに育てられるのと米国で母親ミッシェルに育てられるのと、いずれがより適切であるか」についての判断は一切しないで、原則として、ジョーを直ちに米国に返還することを命ずることになる。以上のような条約適用の流れについて、もう少し補足して説明をしておこう。
まず、この条約の運用に当たって重要な役割を果たす「中央当局」についてである。条約の締約国は、自国の中央当局を定めることになっている。米国の中央当局は、国務省の一部局(Department of State - Office of Children’s Issues)である。各国の中央当局は、他国の中央当局との間で互いに緊密に連絡を取り協力するとともに、自国の他の諸機関とも協力して、この条約の目的を実現するために力を尽くす。具体的には、子を奪取された親(申立人)からの申し立てを受け付けて、子の所在する国の中央当局にその申し立てを伝える(条約8条、9条)。そして子の所在する国の中央当局は、子の迅速な返還を確保するために必要なさまざまな措置を取る(条約7条)。中央当局の働きと援助のおかげで、そうでなければ、外国に連れて行かれた子を取り戻すための数々の困難を前にして途方に暮れるはずの申立人(条約が適用されない場合のミッシェルの気持ちを想像してみてください)は、子を返還してもらうための手続きを実際に利用することができるようになるのである。
次に、どちらの親が育てる方が子にとっていいのかを判断せずに子の返還を命ずることについて。子奪取条約の最も重要なポイントのひとつは、どちらの親に子を育てさせるべきかという判断(すなわち監護権に関する判断)をせずに、実力による奪取があった場合には原則として必ずもとの国に子を戻させるという点にある。もし、奪取された子の返還を求める裁判等において、監護権に関する争いをも含めて判断をしようとすると、将来にわたる子の利益等も考慮しつつ詳しく調べる必要があり、迅速な手続は困難になる。また、場合によっては、奪取してきた者に監護権を与えるべきだという判断がなされて(事例でいうと、カズオが日本で育てる方がジョーにとってより幸福であるという判断がされたような場合)、結局、奪取された子をそのままにするという結論が出ることもありうる。しかし、それでは、条約の目的のひとつである、子の奪取を抑止する効果は、期待できない。そこで、この条約に基づく返還プロセスにおいては、監護権に関する判断はせずに(つまりどちらの親に育てさせるのが子にとって長期的にいいのかということ等は考えずに)、実力による奪取がなされた場合には、そのことだけをもって、もとの国(子の常居所地)に返させることを定めている。条約は、そのように子をもとの国に戻したうえで、監護権に関する判断は、もとの国の裁判所がじっくり調査して判断すればよいし、そうすべきであると考えているのである。以上の点は、条約の16条、17条、19条等に具体的に規定されている。たとえば、17条は、「申し立てを受ける国において監護に関する決定がなされていること」が、この条約に基づく子の返還を拒否する理由にはならない旨を定めている。したがって、父親カズオが米国からジョーを無断で連れて日本に帰ってきた場合に母親ミッシェルが日本の裁判所に条約に基づく返還を申し立てたときには、条約に基づく返還申し立ての要件が満たされていれば、たとえ日本の裁判所がジョーの監護権をカズオに与える旨の裁判をしていたとしても、日本の裁判所はそのことを理由にして返還を拒否することはできないのである。ただし、日本の裁判所は、ジョーを米国に返還するか否かの決定に際し、それまでになされた監護に関する決定の理由を考慮に入れることはできる。
この条約が、このように、国境を越えた子の奪取があったときには、迅速かつ網羅的、確実にその子をもとの国に戻すことを大原則とするのは、たとえ実力で子を奪取して連れてきても無駄であって、かならずもとの国に戻されるということにしておけば、そのこと自体が奪取に対する抑止力として働くであろうという考え方に基づくものである。そして、奪取が生じること自体が子の福祉に対する重大な侵害であることを考えれば、奪取の抑止は、国際社会の目指すべき非常に大切な目標となるのである。
もっとも、この原則には、若干の例外が定められている。まず、奪取から1年を経過してから申し立てがなされた場合であって、「子が新しい環境になじんでいること」が証明された場合には、申し立てを受けた国は子の返還を命じる義務を負わない(12条2項)。逆に言えば、奪取から1年以内に申し立てがなされれば、子が新しい環境になじんでいても返還しなければならないのである。また、条約13条にも、申し立てを受けた国が返還を命じなくてよい例外的な場合が列挙されているが、このうち実際によく問題になるのが、13条1項b号の定める例外である。すなわち、同号によれば、「子の返還が子の身体もしくは精神に危害を加え、またはその他許し難い状況に子をおく重大な危険がある」ことが証明されると、返還義務はない。たとえば、返還先で子が虐待を受ける恐れがあるような場合がこれに当たる。ただし、この例外規定は狭く解釈されており、返還先の国が子を虐待から守ることができる場合には適用されない。
さて、以上に概観したように、子奪取条約が適用される場合と適用されない場合とでは、奪取された親や子の救済が大きく異なる。冒頭に述べたように、すでに81カ国という多数の国がこの条約の締約国になっていることもあり、最近では、日本がこの条約にまだ入っていないのはなぜか、また日本は近い将来この条約に入ることができるのか、入るべきなのか等について、さまざまな議論がなされてきている。
離婚や子育てに関する日本の文化・伝統が、この条約への加入を妨げているのではないかという見方も一部にはあるようである。確かに、日本では、離婚後は一方の親のみが子の親権をもつことになっていて、欧米のような離婚後の共同親権はとられていないし、また、いわゆる面接交渉権も欧米と比較するとやや弱いものになっている。さらに、親が相手方から子を奪ってくることについて、これを子への愛情の発露と考え、国家がこれを強く非難することを疑問視する見方もないではない。しかし、離婚後も、両親がそれぞれの仕方で子育てに関与し、また監護している親以外の親も面接交渉等を通じて子と交流を持つことが、子の健全な発達のためには望ましいという考え方は、近年では日本でも広く共有されてきている。また、親が実力で子を奪取することに対する否定的な評価も高まってきているように思われる(そのような親に刑事罰を課することが最近では実際に行われるようになってきている)。したがって、仮にこのような文化・伝統がこれまで条約への加入の妨げになってきたとしても、今後はそれほど大きな障害にはならないように思われる。
しかし、だからといって、この条約に加入するのが日本にとってごく簡単なことであるというわけではもちろんない。条約に加入するためには、さまざまな点に関して、周到な準備が必要となる。たとえば、中央当局がその任務を果たせるように、人的・財政的な資源を十分に確保する必要がある。また、子の返還を命ずる裁判についても、現存する法的手続きでは不十分であるため、新しい特別な手続きを立法する必要がある。さらに、子を奪取した親が子の返還命令に従わない場合に、その命令を強制的に実現する方法も検討しておく必要がある。また、国内事件として発生する子奪取紛争の解決方法と、条約が適用される国際事件としての子奪取紛争の解決方法との、整合性・バランスも考える必要があろう。
このように、加入のために検討すべき課題は少なくないが、この子奪取条約に加入することによって実現される利益は決して少なくない。条約加入によって、日本への子奪取だけではなく、日本から(他の締約国への)子奪取も抑止されて、子の福祉は全体として大きく改善されることになる。また、現在は、面接交渉等のために日本に子を一時的に旅行させることを認めると、もし約束に反してそのまま子が日本に留めおかれたときに効果的な返還実現手段がないために、たとえば米国の裁判所は子の日本への旅行を認めない傾向にあるといわれているが、日本が条約に加入すればその点は現在よりも認められやすくなるはずである。日本にとってこれらの利点があるというだけではなく、国際的な協調に基づいて世界の子供たち全体の福祉向上に貢献できるという観点からも、この条約への加入は真剣な検討に値するものといえるのではなかろうか。
早川眞一郎
東京大学教授(大学院総合文化研究科・国際社会科学専攻)。東京大学法学部卒業(1978年)。東京大学法学部助手、弁護士(長島大野法律事務所)、関西大学助教授、名古屋大学助教授、東北大学教授を経て、2005年から現職。ハーグ国際私法会議の扶養条約プロジェクトに日本代表として参加。著作に「フランスにおける外国法の適用」名古屋大学法政論集159~162号(1995-96年)など。

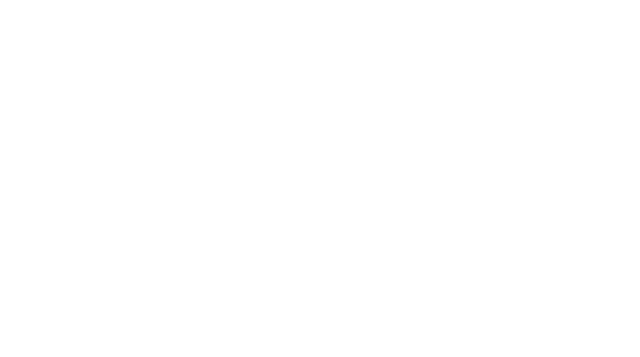



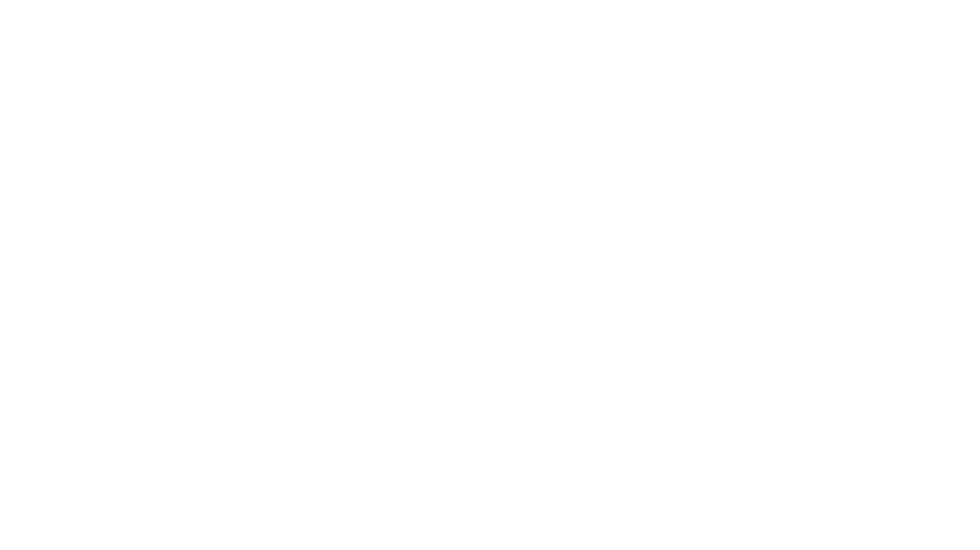
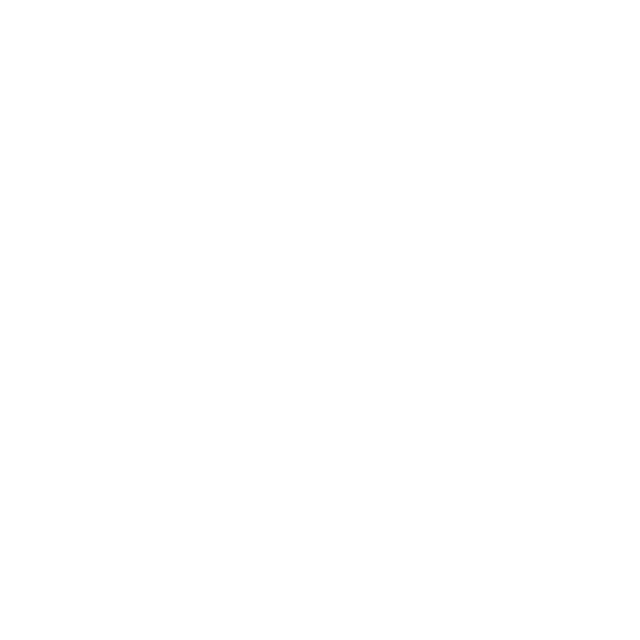
COMMENTS0
LEAVE A COMMENT
TOP