国立アフリカ系米国人歴史文化博物館は、「ソウルの女王」アレサ・フランクリンの逝去に際し、哀悼の意を表します。彼女は、20世紀から21世紀にかけ多くの人々をとりこにした歌手の1人で、その比類なき歌声はアメリカの音楽シーンを変容させました。
少女時代のフランクリンにとって音楽レッスンといえば、ほとんどが彼女の父C・L・フランクリンが牧師を務めていたデトロイトのニュー・ベセル・バプテスト教会でゴスペルを歌うことでした。十代前半にはプロとして歌い始め、1960年にコロンビア・レコードと契約、ミュージカル曲やスタンダードナンバーなどをレコーディングしました。1967年にアトランティック・レコードに移籍、アラバマ州のマッスル・ショールズでレコーディングした「貴方だけを愛して」(原題:(I Never Loved a Man (the Way I Love You))をきっかけに、歌手としてのキャリアが一気に開花しました。
1970年代初めには、アレサ・フランクリンは、既に伝説的な存在となっていました。彼女の歌声はソウルそのものでした。彼女と他の歌手との明らかな違いは、彼女が幅広いジャンルの音楽をレコーディングしてきたことや類まれなる美しい声を持っていたということではなく、彼女の音楽に対する飽くなき探究心と知性にありました。豊かな声質と幅広い音域を持つフランクリンは、詩の区切り、多彩なリズム、ダイナミックな歌い方や多種多様な音色など、アフリカ系アメリカ人のゴスペルをルーツとする音楽要素を自在に操り、自らが持つ音楽的才能を発揮しました。歌詞の1音節に対していくつかの音符を当てるメリスマという技巧をポピュラー音楽に取り入れたのも彼女でした。
私は、フランクリンが「ソウルの女王」の称号にふさわしい歌手であると認識していました。しかし、私がその本当の意味を理解したのは、1998年のグラミー賞で彼女のパフォーマンスを見た時でした。グラミー賞の舞台で彼女は、プッチーニのオペラ「トゥーランドット」のアリア「誰も寝てはならぬ」(原題:Nessun Dorma)を歌い上げました。このアリアは、男性テナー用に書かれた非常に難しい曲で、最近ではイタリアのテナー歌手ルチアーノ・パバロッティが歌って人気を集めました。体調を崩したパバロッティに代わって急きょ舞台に立ったフランクリンは、彼の代表曲であるアリアを、自らのスタイルへと昇華させ、見事に歌い上げました。私はその場にくぎ付けになり、世界もまた彼女のパフォーマンスに酔いしれました。

ホワイトハウスのゴスペル音楽祭に招かれ、グリーンルームとイーストルームの間の戸口で出番を待つ「ソウルの女王」アレサ・フランクリン。本番直前のほんの数秒間、静かに目を閉じている姿に気づいた。ピート・ソウザ撮影のホワイトハウス公式写真。
世界にとってアレサ・フランクリンの存在とは何だったのかと考えるとき、私はソウル・ミュージックの本質を思い起こします。一般的に「ソウル」とは、ゴスペルやR&B(リズム・アンド・ブルース)、また程度の差はあれど、ロックンロールと関連性がある音楽と定義されています。ソウルはまた、抑えきれない感情で満たされた魂を、あるがままに受け入れることでもあります。「ソウル」をこのように捉えれば、アレサ・フランクリンが「ソウルの女王」と呼ばれたゆえんを理解できるでしょう。
フランクリンの遺産は、音楽の1ジャンルへの深い造詣や時代を超えた人気だけに限ることはできません。彼女の歌声は、人々を何か大きなものへと導き、彼ら自身の感情や自分たちが気付かない感情へと結び付けてくれました。何を歌おうとその核心部分で彼女が伝えた情感の細やかさは、芸術のなせる業にほかなりません。
彼女の歌声は、どのような歌であっても、常に我々を感動させました。もし音楽の本質が我々が内なる自分を知り、新たな高みに到達するよう導いてくれることにあるならば、それは、音楽に耳を傾け、自分が自分らしくいる術を教えてくれた「ソウルの女王」アレサ・フランクリンのおかげです。

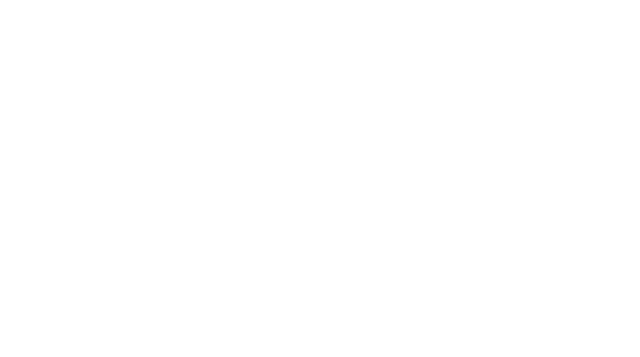



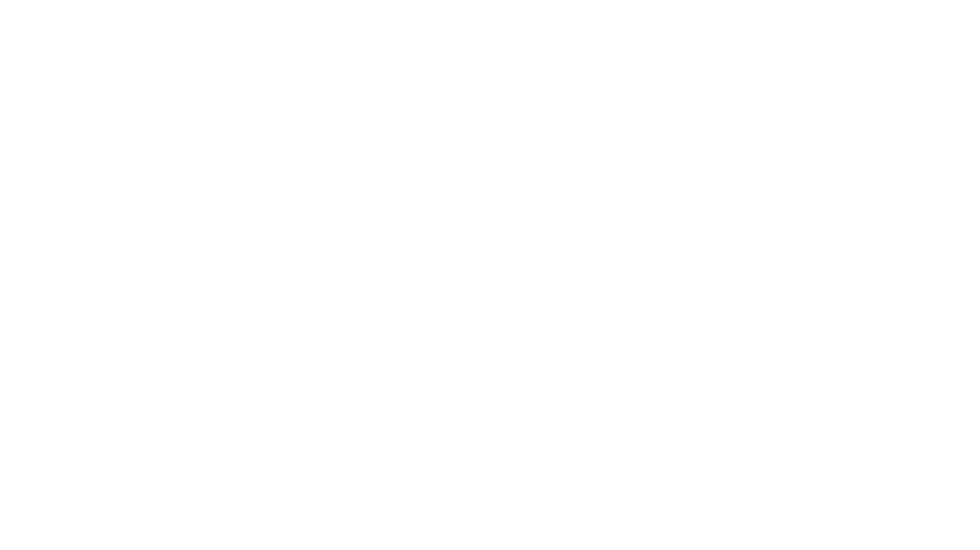
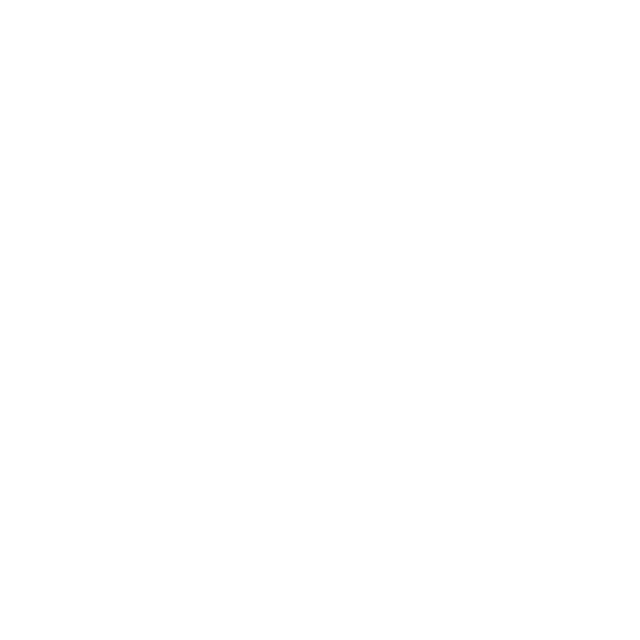
COMMENTS0
LEAVE A COMMENT
TOP