アメリカ料理と言えば、昔から連想されるのが、ハンバーガー、フライドポテト、こってりしたディップソースにチップス、ミルクセーキなど高脂肪、高炭水化物の無粋な料理ばかり。しかしこのところ、こうしたアメリカ料理に変化が見られる。多様化する移民社会や食生活を追い風に、アメリカ人の間で最近、通好みの、冒険心にあふれた料理の創作がはやりだした。
この流行は、1990年代から2000年代初めにフードネットワークなどのテレビチャンネルで人気が高まった有名人シェフの台頭に端を発する。こうした現象は、デジタル時代が到来し、人々が外食する際に、レストランの口コミや食欲をそそるような凝った盛り付けの写真をインターネットで確認できるようになるとともに拡大した。“foodie”という英語の言葉は少なくとも1980年代から料理批評家の間で使われるようになったが、今では口コミで広まったお店を次から次へと食べ歩き、SNSに写真やレビューを投稿するトレンドに敏感な「食通」を指すようになった。

フィラデルフィアのピザ・ブレイン。このレストランではピザ関連の写真やビデオ、雑貨などを眺めながらピザを楽しめる(AP Photo/Matt Rourke)
私の出身地、フィラデルフィアは、食通たちを魅了する斬新なお店であふれている。非常に人気が高いのが「ピザ・ブレイン」。ピザ関連の品々が展示されている博物館の中で、リンゴやアーモンドといったおもしろいトッピングをのせたグルメ・ピザを味わえる。「フェデラル・ドーナツ」は、グレープフルーツ風味の黒糖をかけたドーナツや細かく挽いたコーヒー豆をまぶした「グッド・コーヒー」ドーナツなど一風変わった味を提供する。「ハイ・ストリート・キッチン」では、メキシコ料理の定番ブリトーをすし風にアレンジした「スシ・ブリトー」をファーストフード感覚で味わえる。チョコレートと菓子の専門店「トレイドストーン・コンフェクションズ」がオープンしたころには、洋梨キャラメルキャンディーや青かびチーズ・ホワイトチョコレートなどの斬新な組み合わせに驚く人は、もはやいなくなったようだった。
当然のことながら、この傾向はフィラデルフィアに限られたことではない。サンフランシスコには、こだわりのサンドイッチ店が数多くあり、皮がパリッとしたフランスパンにベトナムのポークソーセージと癖のある野菜をはさんだサンドイッチなど、アイデアあふれる品を提供している。ニューオーリンズで最も有名なフローズンデザートの屋台では、ショウガとカイエンペッパーをかけたかき氷をはじめ、珍しい組み合わせのかき氷を売っている。新しい味を試してみたいという気持ちは誰もが持っているが、珍しい食べ物が増えている理由は必ずしもそれだけではない。今や異国の食べ物を味わうこと、国の食文化だけでなく、地域特有の食文化を知っていること(あるいは、少なくとも知っていると主張すること)が「クール」とされているのだ。「新鮮さや独特の風味を楽しみ、食べ物にまつわる話をしながら料理を味わう、より洗練された新しい経験が、注目を集めつつある」。食や栄養補助食品の市場動向に詳しいA・エリザベス・スローンは昨年、食の専門誌「フード・テクノロジー」でこのように語った。
このような動きに批判がないわけではない。美食家たちは“foodie”という言葉を嫌い、その言葉が包含するマイナスのイメージ―ものを食することとは、エリート意識を持つ、もったいぶった人間がスリルを求めてする行為―から距離を置こうとする。批評家のなかには、珍しいフレーバーを加えることに異論を唱える者もいる。確かにハニーマスタード風味のアイスクリームを作ることはできるが、本当にバニラアイスよりもおいしいのだろうか?
しかしながら、アメリカ本土の若者の間では斬新な料理への人気は高まる一方だ。この動きが個人の支出に与える影響について、ワシントン・ポスト紙は「食通」文化がロックンロールに取って代わっていると示唆する記事の中で触れ、「2000年から2011年までの間で25歳未満のアメリカ人が年収のうち外食にまわす金額は約26%、25~34歳の年齢層では約20%増加した」と報告している(数値は米国労働統計局のデータに基づいており、物価変動を考慮していない)。
もう1軒、フィラデルフィアで食通たちが足しげく通う店にアジア・フュージョンレストランの「チュー・ヌードル・バー」がある。お店に行ったとき、私が注文したのはシェフお勧めの唐辛子スープの牛肩ばら肉ラーメンで、キムチとユダヤ人の大好物の大きな団子「マッツァー・ボール」がトッピングされていた。
- チューヌードルバーの看板
- チューヌードルバーの人気メニュー

フィラデルフィアにある「チュー・ヌードル・バー」店内の様子
「最初のころ、本物のラーメンではないと思ったお客もいたよ。その通り。僕は本物のラーメンの作り方を知らないからね。本物のアジア料理をまねようとしているのではなく、そこから進化したものを提供したいと思っている」とエグゼクティブシェフのベン・プチャウイッツ氏は語る。
「僕にとってこれは、アジアの材料を使ってアジア風の味付けをしたアメリカ料理。その意味ではフュージョン(融合)といえるね。でもアジア料理の技法を取り入れて、皿の上でアメリカ料理の技法とミックスするのとは違うんだ。どちらかといえば、文化と食の融合だよ」とプチャウイッツ氏は説明する。
私は個人的には、チューの「ラー油かけ牛肉餃子」のファンだ。これを食べると四川料理のレストランで出される料理を思い出すが、何ともいえない他の風味も混じっている。プチャウイッツ氏は、父親が四川風鶏肉炒めを家で作ってくれた思い出を話してくれたが、私の家では母が日本の「野菜炒め」を模したオリジナルの料理を作ってくれた。だからこの折衷主義の広がりは決して新しいものではない。都市に住むアメリカ人は昔から、テイクアウトした食べ物や、さまざまな文化的背景を持つ「ご近所さん」が作る料理からヒント得て、家庭で料理を作ってきた。ひょっとしたら食通たちに人気のフュージョン料理のお店は、ようやく家庭料理に追いついてきたのかもしれない。
そこで、今やどこでも買うことができるハニーマスタード味や焼きトウモロコシ味、アールグレイ・チリソース味などの奇抜なアイスクリームについてプチャウイッツ氏に聞いてみた。彼が目指しているのは、今までにない味を作り出すことではなく、料理を進化させることだ。なので彼から答えを聞き出せないかもしれないと思ったが、そんなことはなかった。彼の答えはこうだった。「新しいアイスクリーム店は、チョコレートアイスやバニラアイスを提供するためにオープンしたわけではない。お客さんがそのために来店してくれるようなものを提供しようとしている。そして客は、他とは違うものが提供されるからこそ、足を運ぶ。おいしいとか、まずいとか関係ない。違うものが味わえるから客が来る。常に変化を求めるのがアメリカ人なのさ」

「チュー・ヌードル・バー」エグゼクティブシェフのプチャウイッツ氏(写真左)と共同経営者のショーン・ダラー氏
 キャシー・オーウェンズは、フィラデルフィアを中心に主に都市や文化について執筆するフリーライター。フィラデルフィアのオンライン情報サイト「Next City」、Philadelphia City Paper紙、CNN.com 、Jewish Daily Forward紙など多数の出版物に寄稿している。Twitterアカウントは@cassieowens
キャシー・オーウェンズは、フィラデルフィアを中心に主に都市や文化について執筆するフリーライター。フィラデルフィアのオンライン情報サイト「Next City」、Philadelphia City Paper紙、CNN.com 、Jewish Daily Forward紙など多数の出版物に寄稿している。Twitterアカウントは@cassieowens
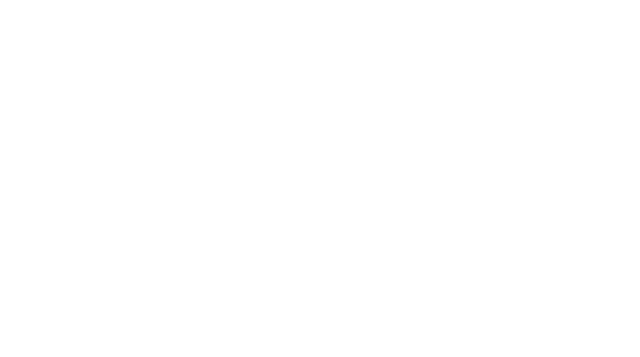



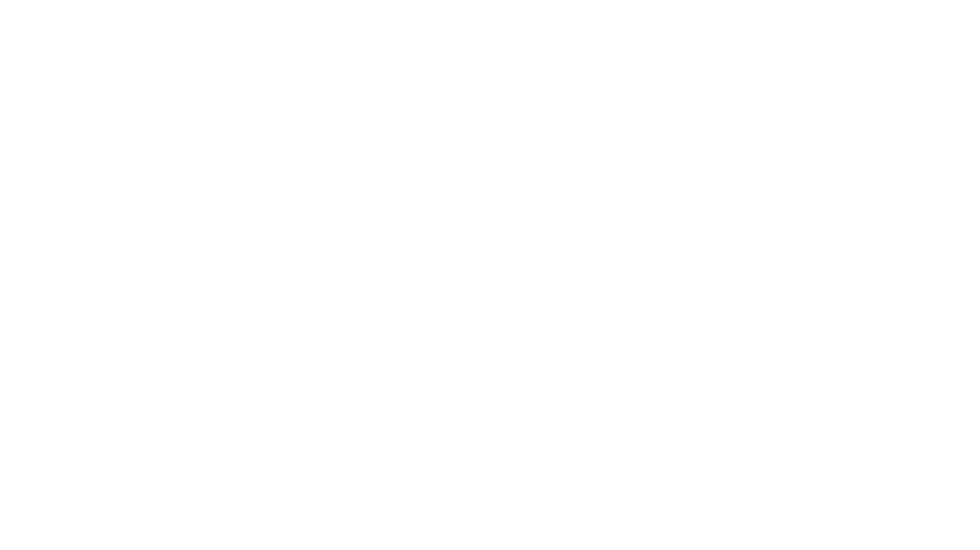
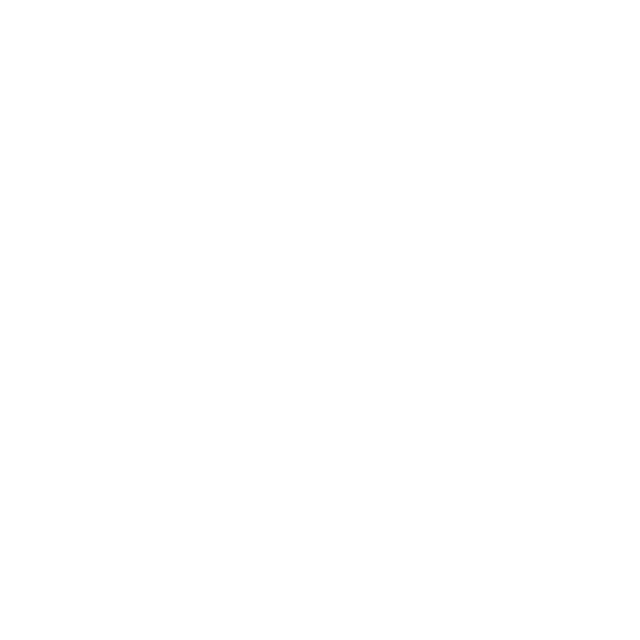


COMMENTS0
LEAVE A COMMENT
TOP