ペンシルベニア大学の博士候補者のマーク・ブックマンさんは、日本に何度か留学した経験があります。初めての来日は高校生の時で、その当時の関心はラーメン店での食べ歩きやアニメ雑誌で、アクセシビリティ問題を深く考えることはありませんでした。しかし、仏教を研究するためフルブライト研究員として再来日した時、彼を取り巻く状況は複雑になっていました。車椅子生活をするようになっており、身の回りのさまざまなことを自分でやらなければならなかったのです。「私の生活はジグソーパズルに似ています。ベッドから起きる、学校に行く、研究をする、家に帰る、食事をする、寝る、そしてそれを繰り返すといった行動は、パズルのピース一つ一つを正しい場所にピタリとはめこむ作業のようなものです」と、ブックマンさんは言います。
アクセシビリティを地図化する考えは、フルブライト留学を終えた後に思いついたと言います。アクセスに関する物理的、社会的な障壁についてのデータをリアルタイムで共有できるクラウドソーシングのアプリケーション「アクセシビリティ・マッピング・プロジェクト(AMP)」を開発。現在は東京大学の客員研究員として日本に滞在し、同大学で世界中の障害者が直面する教育、雇用、社会参画の障壁を取り除くツール開発や戦略立案に携わっています。またアクセシビリティのコンサルタントとしても活躍し、アクセシビリティ問題に関する記事を内外の媒体に寄稿しています。
2020年1月、ブックマンさんは在日米国大使館が主催するアクセシビリティ問題に関するパネルディスカッションに参加、モデレーターを務めました。アメリカン・ビューはブックマンさんにインタビューを行い、AMPやアクセシビリティに関する考えを伺いました。
アメリカン・ビュー:開発したAMPについて教えてください。
ブックマン:AMPの着想は、私の学生としての経験から生まれました。大学院に入った当初、「アクセス可能」と書かれた場所の多くは、実際にはアクセスしにくいことに気がつきました。例えば、車椅子対応ドアから建物に入っても、その建物内のトイレはどれも車椅子で入れなかったことがありました。また、車椅子対応ドアから入ろうとしても、そのドアは違うサイズの車椅子に合わせてあり、結局入れなかったこともあります。キャンパス案内図に書かれていることは、アクセシビリティの面においてはどれも非常にあいまいであることに気が付きました。そこで私はもっと知りたいというだけでなく、自分の経験を共有したいと思うようになりました。さらにこれは、私だけの問題ではないことも分かっていました。他の障害者も同じような問題を抱えていたはずです。情報共有をよりよい方法で進める必要があると考え、どのような機能が障害者に対応しているか、またしていないかといった情報を共有できるデジタル地図を作ろうと動き出したわけです。このような情報を多くの人と共有することで、誰もが使いやすい環境整備に向けて協力できるようになりました。これは使命でした。
アメリカン・ビュー:日本とアメリカ両方の学校で勉強した者として、アクセシビリティの面で大きな違いを感じたことがありますか。
ブックマン:合理的配慮の仕組みで違いがあります。アメリカでは1991年以降、学校には合理的配慮が義務付けられています。一方、日本ではこの仕組みが2016年に導入されたばかりです。日本ではまだこの仕組みの下で学校を終える障害者が少ないため、学校側はどのように対応してよいのか分からないのが現状です。障害者は教育にアクセスできないため、職探しに苦労する場合がよくあります。これは障害者が自立した生活を送る、自分で決めた人生を歩む能力に影響を与えることになります。しかし日本のアクセシビリティ基準が私にうまく機能しないことがあるように、アメリカの基準も留学している日本人学生に適さないことがあります。どちらの国の仕組みがいいとか悪いとかという問題ではありません。日本とアメリカは単純に違うということです。理想的な基準に合わせるのではなく、あらゆる人を受け入れるために何ができるか。学校全体のアクセシビリティの真の問題はここにあると思います。
アメリカン・ビュー:海外留学を考えている障害を持った学生に何かアドバイスはありますか。
ブックマン:まず全てを予測することは不可能という認識を持たなければなりません。つまり柔軟な行動が必要となります。空港に着くことはできても、そこから学校の寮まで移動することはできないかもしれません。電車を使うことも無理かもしれません。タクシーをつかまえなければならないかもしれません。でもどうやって? その解決策の一部として、インターネットでの事前調査や学校側との調整をお勧めします。留学とは、ただ学校に行って授業を受けることではありません。情報通の地元ネットワークの活用が必要となります。それは障害者団体かもしれませんし、キャンパス外で活動する学生グループかもしれません。

TEDxFulbright Tokyoにて「希望としてのパラリンピック ― アクセシビリティの過去、現在、未来」というテーマで講演するマーク・ブックマンさん。2019年3月17日撮影
アメリカン・ビュー:今年で「障害を持つアメリカ人法(ADA)」制定から30年を迎えます。この法律により障害者の生活はどのように変わったと思いますか。
ブックマン:私はADAが成立した年に生まれたので、私の人生はこの法律から大きな影響を受けています。私が全ての学校に通えたのも、あらゆるプログラムに関わることができたのもADAがあったからで、この法律の重要性を十分に理解しています。ADAは当初目指していたこと以外にも、人とのコミュニケーションを可能にし、アクセスしやすい世の中を開いてくれました。これはアメリカだけでなく、日本でもそうです。ADA可決直後、アメリカの障害者権利を訴える活動家のグループが来日し、ADAについて語り、日本企業と協力しADAの仕組みの中で国際ビジネスを可能にする基準づくりを行いました。ADAは国境を越えて大きな成果を生み出しました。ADAを画期的な法律でないというのであれば、それはADAを軽視していると言えるでしょう。
アメリカン・ビュー:ADAを超えたアクセシビリティに向けた次のステップは?
ブックマン:ADAの最大の問題は、訴訟に頼って変化を生み出そうとしているところにあります。例えば、私があるレストラン行くとします。そのお店の前にはあってはならない段差があります。私がこれを変えたいとしたら何ができるでしょうか? ADAに基づいて訴訟を起こすことができます。しかしそれには、時間、お金、エネルギーが必要となります。訴訟が終わった頃には、そのレストランは店を畳んでいるかもしれません。命に関わるような問題でない限り、訴訟を起こす価値はありません。ADAだけでは十分ではありません。社会的な圧力が必要となります。日本の場合に変化を起こす強いきっかけとなるのは、高齢化かもしれませんし、オリンピックのようなイベントかもしれません。変化を起こすには何らかの刺激がなくてはなりません。
多くの企業は、アクセシビリティを障害者のための特別な配慮と考えています。しかしその考えに欠けているのは、アクセシビリティは障害者のためだけのものではないということです。ベビーカーを押しているお母さんやお父さんもいれば、高齢者もいます。もしアクセシビリティを、障害者を助けるためだけのものではなく、万人を社会に参画させるものと捉えれば、驚くようなことが達成できると思います。
バナーイメージ:在日米国大使館が主催するアクセシビリティ問題に関するパネルディスカッションに参加し、モデレーターを務めるマーク・ブックマンさん。2020年1月撮影

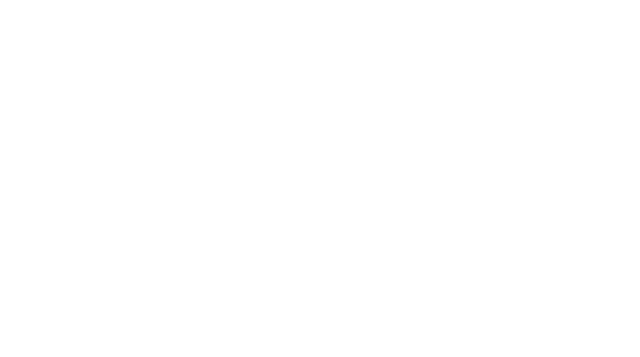



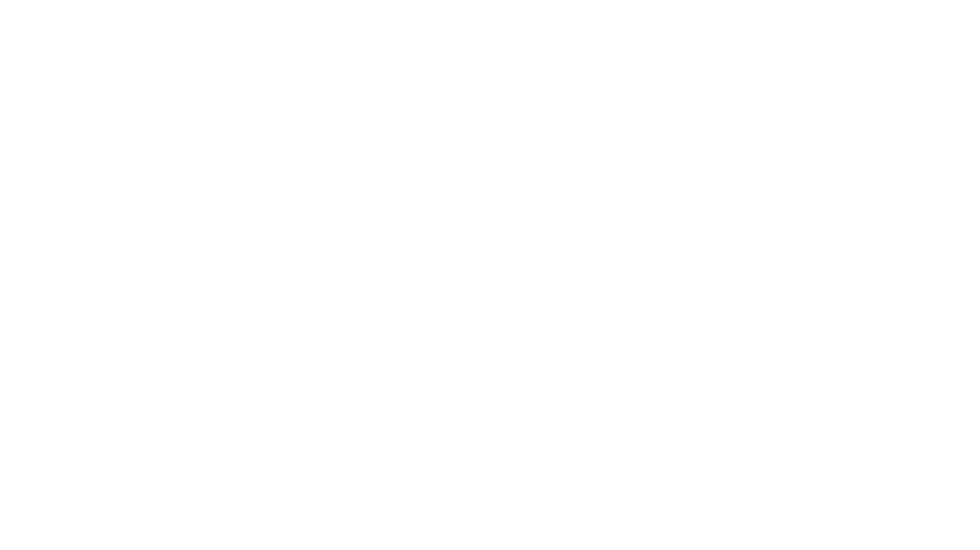
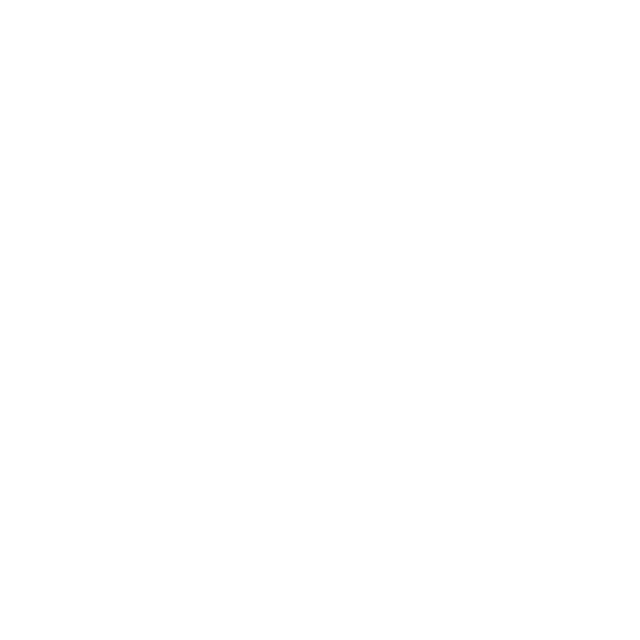
COMMENTS0
LEAVE A COMMENT
TOP