目を閉じれば、走馬灯のように、アイオワシティの晴れやかな空と町、アイオワ大学国際創作プログラム(IWP)の親しき顔が浮かんでくる。幸運なことに、2019年秋、わたしはそのプログラムに招待された。日本の女性詩人の参加は、約20年ぶりとのこと。
夢のような3ヶ月間だった。今年のIWPには、アジアは、香港、韓国、台湾、中国、インドネシア、ミャンマー、シンガポール、ネパール、日本。中近東とアフリカからは、トルコ、イスラエル、モロッコ、ジンバブエ、アルジェリア、マラウィー、ナイジェリア、エリトリア、ナミビア、南アフリカ。ヨーロッパからはチェコ、ラトビア、リトアニア、ギリシャ。ラテン・アメリカからはメキシコ、アルゼンチン。合計25カ国、28人のIWP writers、詩人、作家、批評家、劇作家、放送作家等々が集まった。既存のヒエラルキーを越え、あらゆるエスニシティや文芸ジャンルを公平に捉えて応援するIWPの姿勢は、したたかな知性のかたまりとも言える。この先、何が文学になるのか、何がその価値を牽引するのか、もはやだれにもわからない時代。その複雑さを見すえた上で、文学の「未来」をできるかぎり展望しようとしている。
さらに、学生時代に戻ったかのように屈託ない交流をかわすIWP writersは、自作朗読、講義、パネル・ディスカッションなど、発表の場も担当。それらの催しには、アイオワ大生だけでなく、文学に関心のある市民たちも数多く来場したが、2008年にユネスコの文学都市に指定されたアイオワシティには、土地に根ざした文学への愛がある。
ともあれ、わたしにとっては、講義やパネル・ディスカッションを英語でするのは厳しいハードルだった。ほかのIWP writersが、時々ジョークで沸かせながらユニークな発表をし、会場からの質問にも即妙に答えているのを見たときには、絶望に近い衝撃をうけた。体力のつづく限り、writersが集うパブに通い、わいわいおしゃべりし合ったのは、わずかでも英語を上達させたい意図もあったのだ。
それらの体験を通して学んだことを一言にすれば、国際的な説明能力と言っていいように思う。語学力のみならず、何を主張する作品なのか、どんな思想や興味のもとに書いているのかを示す能力。アイオワの学生も市民も、わたしの作品や経歴を知らない。そこにひとりで立って、何を伝えたらいいのか。
広大なアメリカで自作朗読が親しまれているのも、おそらく同じ理由からだろうが、じぶんの作品は、まずみずからが声に出して届け、その背景にある姿勢を説くことが求められた。聴衆が興味を持てば、本が売れ、そのうち批評へつながっていく。
幸い、わたしは、ジェフリー・アングルスの優れた編集手腕によって、新しい英訳詩集『Factory Girls』を、前衛的な翻訳詩の版元として知られるAction Booksから滞在中に出版することができた。そこで、自作詩の朗読とともに、日本の地方都市、群馬県桐生市の織物工場で生まれたこと、その産業の栄枯盛衰を幻想的な叙事詩にしたためてきたことを説きつつ、いわゆるスタンダードな「日本語」を越え、土地言葉の響きやリズムをとり入れることで、新しい詩のことばをつくる挑戦を語った。言語は、そもそも national(国別)でも local(地域別)でもなく、 individual(個人別)なものではないかという思考が、わたしにはある。

書店での IWP 一般公開イベントでジェフリー・アングルスとともに自作詩を朗読する
また、監督の鈴木余位と組んで企画制作した映画『東北おんばのうた ――つなみの浜辺で』の暫定版がひとまずまとまり、催しの一つとして上映できたことも思い出深い。この映画は、拙著『東北おんば訳 石川啄木のうた』の出版を通じて知り合った、岩手県大船渡市のご年輩女性(おんば)のドキュメンタリーだが、アイオワ大学准教授のケンダル・ハイツマンとその授業「日本文学翻訳演習」の受講生が英語字幕を作ってくれたのである。上映会には100人近い観客が来場し、大盛況だった。
さらに何より、WhatsAppなどでいまも連絡をとり合っているIWP 2019、ファミリーと呼び合うほど親密になった面々との出会いとつき合いは、なんと輝かしかったことか。

IWP 2019の参加 writers 一同とともに
IWPのディレクター、クリストファー・メリルに無事の帰国を連絡すると、日米に頑丈な橋を架けてくれたタカコに感謝すると返信が届いた。日本からのバトンが続くことを祈りつつ、IWPの最大の支援者であり、渡航を助成してくれたアメリカ政府にこの場を借りて感謝したい。
***
月が昇ると、 新井高子詩集『タマシイ・ダンス』より
だれもいない紡績工場の夜勤です
電球はひとつだけ、
ひとりでに糸車が回っていて
カシャン、というのは
ボビンがとり替えられる時の音です
ここが終いになって
もう十年たちますが、
月が昇ると、働きはじめるのです
珍しいオートメーション
戦後まもなく
機械に髪を巻き込まれ、
亡くなった女工さんがあったそうですが、
幽霊のしごとではありません
いえ、
漂うものもあるのですが、
工場にも、
癖がある、
こういうことです
癖というのは残りますから、
四十四年、糸繰りをしたばあさんは
今際の床でも
人さし指の先を舐めては撚り上げる、
そのしぐさから逃れることができません
冥土でも、そうでしょう
糸というのは限りなく細いですから
操つるものたちの肉体に
かえって身ぶりが染み込んでしまうのです、
とり憑いてしまうのです
ほら、
女工さんの手先から
すうっと、
生糸を引き抜けば、
いつまでも踊っているではありませんか
工場もそうです、
糸車の芯棒が
覚えてる、
鉄の粒子は
回りつづけていた向きに
もはや頭を垂れたままなのですから、
ガラン、
と乗りだします
月光がそそぐとき、
満ち干があるのは潮ばかりではないのです
ガラーン、
ガラーン
糸車が回ってる、
糸たちが泳いでる、
だれもいない紡績工場

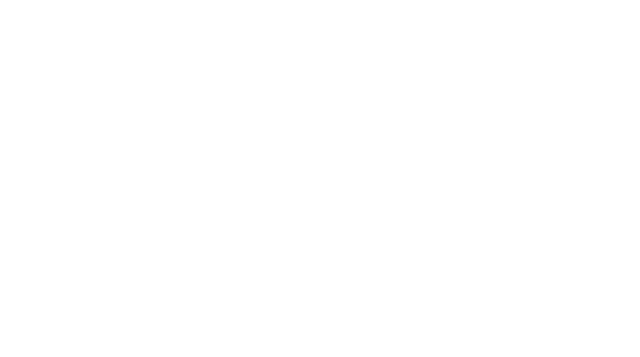



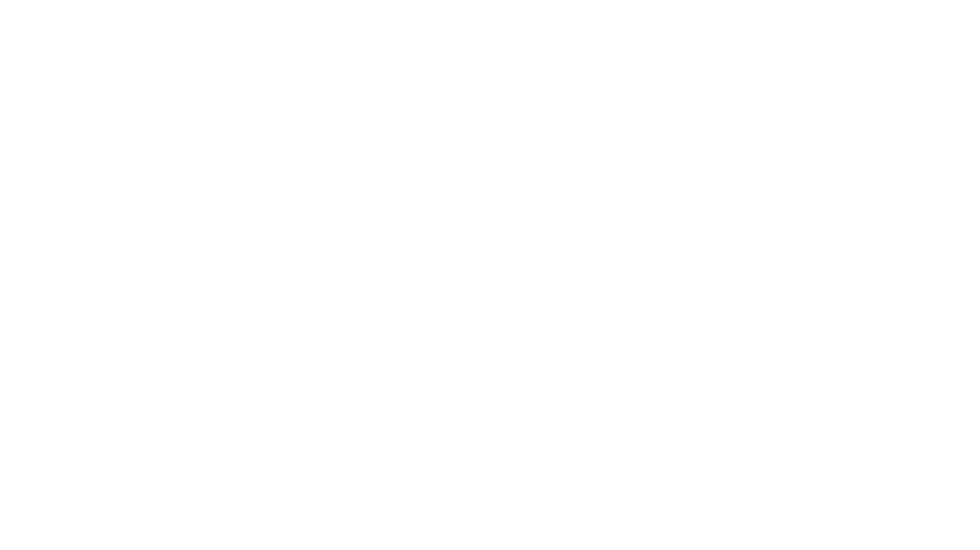
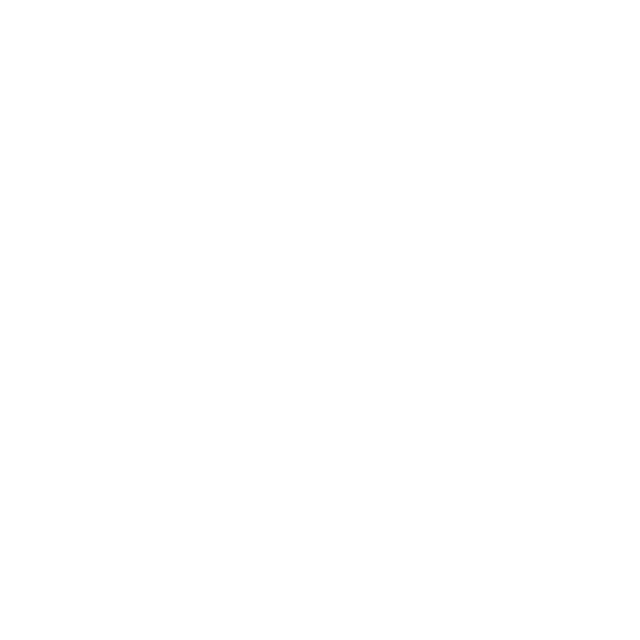
COMMENTS0
LEAVE A COMMENT
TOP